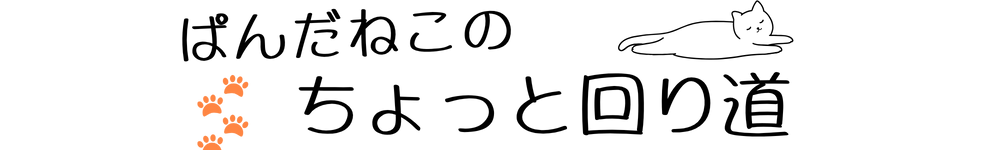旦那の母親と、弟夫婦が島にやって来た。三女はちょうど本土へ帰省中。
弟夫婦はホテルへ。
母親は、我が家に宿泊。
聞けば、母親がこの島に来たのは、19歳の頃。
まだ父親と結婚する前のことだったという。
「あの旅館に泊まったのよ」
「あの灯台の手すりに名前、刻んだ」
島をめぐるたびに、母親はぽつぽつと昔の記憶をこぼしていた。
旦那にとっては「知らなかった父と母の時間」を追いかける、不思議な旅になったようだ。
でも、ワシ(猫)が見ていたのは、家の中での“時間”だ。
久しぶりに、母と子が数日間、ひとつ屋根の下で過ごす。
それはちょっと特別で、ちょっと息が詰まる時間でもあった。
母親は、今は透析治療を受けている。
だから長くは滞在できない。
けれど、その短い時間が、なんとも濃かった。
階段を下りる母の足元を支える旦那の姿に、
ワシは押し入れから、そっと目を細めた。
かつて元気だった頃の母の姿を思い出すたびに、
何とも言えないもどかしさが、旦那の肩に乗っているようだった。
離れていれば、心配がつきまとう。
一緒にいれば、気を使ってしまう。
「面倒だな」と感じてしまう自分に、また罪悪感――
人間って、ほんと、めんどくさい生き物だ。
ある晩、島の知人が母のためにごちそうをふるまってくれた。
その席で、母親はふと目元を押さえた。
「こんなにしてもらって…ありがたいねぇ」
その様子に、旦那もしばらく言葉を失っていた。
旦那の暮らしぶりや、人とのつながりが、第三者を通して母に届いた瞬間。
母は、少しだけ肩の力を抜いていたようだった。
親子って、まっすぐには向き合えない。
でも、ちゃんと想っている。
面倒でも、大切。言えなくても、伝わっている。
母と弟夫婦は島を離れた。
にぎやかだった数日が終わり、
ふたたび、いつもの暮らしに戻る。
朝、ワシが空の皿の前で「にゃあ」と鳴けば――
「カルカン18歳から」は、いつものように出される。
島の時間は、今日も変わらず、
ゆっくり、アナログに流れている。