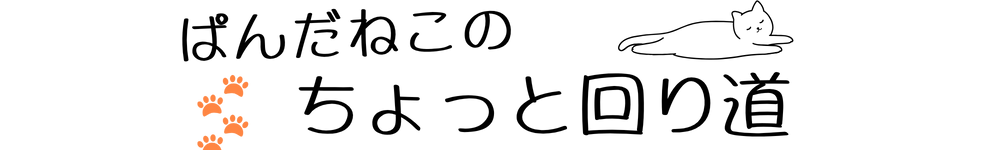本土に一時帰省した旦那。
街は、かつて暮らしていた場所だったのに、
その面影は少しずつ、静かに消えていっているらしい。
「100年に一度のまちづくり」と銘打たれ、
バス停は移動し、歩道橋も姿を消し、駅の場所も変わった。
代わりに、立派な施設が建ち並ぶ。
知っていた風景が、知らないものに置き換えられていく。
それは、きっと悪いことじゃない。
だけど旦那は、心のどこかがひっそりと寂しかったのかもしれない。
昔、その歩道橋の下には、いつもひとりのおじさんがいた。
段ボールを敷いて、誰にも邪魔されない小さな空間。
冬には、あの段ボールを囲って風をしのいでいたのを、旦那はよく覚えている。
でも今は、そこに何もない。
ただの真新しい舗装道路と、にぎやかで整然とした建物たち。
あの頃にあった静けさや、余白のようなぬくもりは、どこかへ消えてしまった。
「もう、街は、自分がかつて過ごした場所じゃないなぁ」
帰ってきた旦那は、ぽつりとそうつぶやいた。
便利になることは、たしかに大事だ。
でも、“人のぬくもり”や、“記憶のしずく”まで流れてしまうのなら、
それは、ちょっとだけ、さみしいことだと思う。
一方、この島にも、変化の波はゆっくり届いている。
けれどまだ、あの頃の空気をまとったまちの営みがある。
古びた看板が風に揺れ、どこからかおばあちゃんの呼びかけが聞こえてくる。
変わらない景色が、変わらない人たちが、ここにはまだある。
それがどれだけ貴重で、どれだけ心の支えになるのか。
人は、きっと、失ってから気づくんだろう。
ワシは今日も、縁側で丸くなって、
潮の匂いと、夕焼けを感じながら、まちの話し声を聴いている。